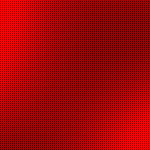運送業において点呼業務は必須なものとなっていますが、正しく行えていると思ったとしても、違反になっている場合や、わかっていても正しいものを実施することが負担となっているケースもあります。
違反にならないためにも、改めて正しい方法について知っておくことが求められます。
運送業における正しい点呼
まず最初に運送業における正しい点呼としては、対面と電話、ITの三つの方法が挙げられます。
対面
対面とは運転者が営業所や車庫の定められた場所で執行者と直接立ち会って行う方法を指しています。
運行上やむを得ない場合を除いては、原則として所属の営業所や車庫などで、乗務前や乗務後に対面で実施する必要があります。
電話
そして電話を使った方法は、1泊2日や2泊3日などのように、宿泊を伴う運行によって、運転手が営業所や車庫などの定められている場所に来られない場合に、電話によって執行者と直接対話で行う方法を指しています。
携帯電話や無線などドライバーと直接対話できるもので行うことが求められ、電子メールやFAXなどの一方的な連絡方法は該当することがありません。
IT
そしてITと呼ばれるものは、国土交通大臣が定めた機器を使って、他の営業所の執行者とテレビ電話のような形でお互いの顔を見ながら行う方法です。
これは営業所が一定の条件を満たしている場合に限ります。
本来は対面によって行われるものを、ITにより他の営業所の執行者と実施することができるので、執行者の負担の軽減や効率化を図ることにもつながります。
点呼を実施する人
どのような人が執行すれば良いのかと言うと、運行管理者の資格を持っている人、もしくは事業者が選んだ補助者が実施する必要があります。
全体の回数の1/3以上は、運行管理者が行わなければならないと定められています。
そしてこの業務を実施した記録は、執行者が所属している営業所やドライバーが所属する営業所の双方で保管しなければなりません。
保管の期間は1年間と定められていて、平成30年からはこの記録は書面による記録や保存に変え、デジタルによる保存も行えるようになってきています。
まとめ
この業務においてどのような確認事項があるのかと言うと、乗務前には執行者名と運転者名、また業務に係る自動車の登録番号、日時や方法などその業務は多岐に渡ります。
記録は確認を義務付けられているものがあり、それらの項目については必ず記録を残す必要があります。
万が一記録漏れが判明すると、再提出を求められることもあるでしょう。
最悪罰則を受ける可能性もあるため、義務付けられている確認事項についてしっかりと把握し、それを守る義務があります。
最終更新日 2025年5月20日 by aequorea